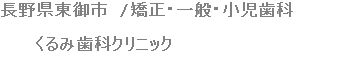歯ぎしり・くいしばりついて
歯が浮いたように感じる、冷たいものがしみる
あごに痛みやだるさを感じる
歯やかぶせものが割れる、欠ける
歯がすりへる
などの症状がある場合は、歯ぎしり・くいしばり(上下の歯を強くかみしめるくせ)が原因かもしれません。

歯ぎしりとは?
食事や会話などとは別に、上下の歯を無意識にかみあわせることを歯ぎしりといいます。起床時や仕事や勉強の後などにあごがだるく感じる方は、気づかぬうちに歯ぎしり、くいしばりをしているかもしれません。
歯ぎしりの種類
歯ぎしりは以下の3つに分けられます。
1、グラインディング いわゆる歯ぎしりのことで、ギリギリと音をたてて強く歯をこすり合わせる習癖をいいます。 就寝中に発生することが多く、歯のすり減りが起こりやすいことが特徴です。
2、クレンチング 上下の歯を強くかみしめる(くいしばり)習癖をいいます。 音を立てることがないため周囲の人に指摘を受けることもないので、症状が出るまで気づきにくいでしょう。
3、タッピング 上下の歯をカチカチと連続的に速くかみ合わせる習癖をいいます。 上記の2つに比べると起こりにくいとされています。
歯ぎしりの原因
歯ぎしりの原因としては様々なものが考えられていますが、現在のところ根本的な原因については不明な点が多く、詳しいメカニズムはわかっていません。
かみあわせの異常や、あごの変位、治療で入れたかぶせものの高さが原因で歯ぎしりが起こる例は少なく、かみあわせが直接もたらす影響は少ないということがわかってきました。
他の原因としてくせ・習慣性や肉体的・精神的なストレス、遺伝、飲酒・喫煙との関係などが指摘されています。
特に睡眠中に歯ぎしりをしているときは、脳に刺激が与えられ、一時的に交感神経が活発になることがわかっており、ストレスを解消するために歯ぎしりをしているのではないかと、という説が有力です。
またアルコールやタバコ、カフェインを取りすぎると歯ぎしりが多くなることも知られています。
子どもにも歯ぎしりは見られます。歯がはえはじめたばかりの時期や、乳歯と永久歯の入れ替え時期に起こることがあります。
子どもの歯ぎしりは、あごや歯が本来収まる位置を決めるために起こっていると考えられています。成長とともになくなることが多いのであまり心配ありません。
歯ぎしりによる症状
●歯や人工物(かぶせもの)が割れる、欠ける、歯がすり減る
●歯が浮いたように感じる、ゆれる
●冷たいものがしみる
●あごに痛みやだるさを感じる、あごが開きづらいなど
歯ぎしりの治療について
治療法には様々なものがありますが、最も簡単な方法としては ナイトガードと呼ばれるマウスピースを装着することで、睡眠時の歯ぎしりの音や、歯やあごへの負担を減らします。 マウスピースは保険で作ることができます。
歯ぎしりの問題点
歯ぎしりにはむし歯や歯周病といったお口全体のトラブルだけでなく、体全体の不調につながる可能性が指摘されています。
寝ている間に歯ぎしりをすると、歯と歯が長時間こすり合わされるので、いつの間にか歯がすり減っていたり、欠けたりということがよく起こります。せっかく歯科治療で入れた詰め物やかぶせものがはずれたり、割れたりすることもよくあります。
また歯がすり減ることにより、冷たいものがしみるという知覚過敏の症状になったり、歯肉へのダメージから歯周病が進行しやすいといった危険性もあります。
歯ぎしりをする方は、常に歯を強くかみしめている傾向が強いので、あごに対する負担も大きくなります。そのため、あごが開きづらくなったり、あごに痛みやだるさを感じることもあります。
セルフチェック
ギリギリと音を立てる歯ぎしりだけでなく、無意識に歯をかみしめている行為も歯ぎしりに含まれます。このような場合、周囲の人にも気づかれにくく発覚が遅れることがあります。左記の症状がある場合は、歯ぎしり・くいしばりをしていないかご自身で気をつけてみることも必要でしょう。
ストレスが原因かもと思われる場合には、マウスピースなどの治療に加えて、日頃からストレスを軽減することが何よりも重要です。眠る前にリラックスする習慣を作ったり、睡眠に悪影響を及ぼす飲酒や喫煙を控えるなど、改めて生活習慣を見直しみてはいかがでしょうか。

くるみ歯科からのアドバイス
①かみしめていると気づいたら→とりあえず口を開きましょう。
②奥歯はかみしめていない状態(奥歯は接していない状態)が本来のリラックスした状態です。
③くちびるを閉じた状態で、奥歯はかんでいない位置を確かめましょう。
④「舌を奥歯に押し付けるようにする癖」「頬の内側の粘膜をかんだり吸い寄せたりする癖」も多いようです。
まず自分で気づくことが大切です。
⑤正しい舌の位置は、舌の先が上の前歯の裏側と上あごの間をさわる感じの位置です。
⑥眠る前に奥歯でかんでいない感じや舌の位置を確かめ、リラックスする習慣をつくりましょう。
⑦寝る前や在宅時、アロマの香りでリラックスするのも良いと思います。
⑧こめかみやあごの関節のあたりを優しくマッサージするのも筋肉が緩んで痛みが軽減されます。
⑨あごが痛くて開きにくいときは無理に開けようとせず安静にしているのが一番です。